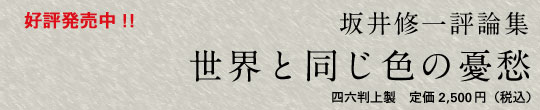|
s |
| ◆
週刊時評 ◆ |
川本千栄・広坂早苗・松村由利子の三人がお送りする週刊時評(毎週月曜日更新)
|
|

第二芸術論の検証
text 松村由利子
二月十日に東京都内で、シンポジウム「いま、読みなおす戦後短歌 2」が開かれた。昨年七月に開催された一回目と同じく、発表者は西村美佐子、秋山佐和子、佐伯裕子、今井恵子、川野里子、花山多佳子の六人である。今回のテーマは「第二芸術論の時代」だった。
各人が二十分ほどの発表を終えた後に合同討議が行われるという形式は前回通
りだったが、今回は内容的なつながりが見えやすく、全体としてまとまった印象を抱いた。これは、発表に先立ち、川野が「第二芸術論」のアウトラインを説明したことが大きかったと思う。配られた資料に抜き出された桑原武夫の「第二芸術−現代俳句について−」、小野十三郎の「奴隷の韻律−私と短歌−」など、「基本的で有名なフレーズ、共有しておくべき内容(川野)」に目を通
した後、それが戦後になって突然現れたのではなく、尾上柴舟の「短歌滅亡私論(明治四十三年)」、釈迢空の「歌の円寂する時」(大正十五年)に端を発するものだったと説明され、とても納得した。「短歌滅亡私論」が発表された明治四十三年という年には、大逆事件や日韓併合があり、人々の閉塞感ややり切れない思いに満ちていたという指摘も非常に鋭いと思う。
この小さなレクチャーに続いて、六人それぞれの発表が行われた。発表者とテーマは以下のとおりである。西村美佐子・「八雲」からみえてくるもの▽秋山佐和子・「人民短歌」「郷土」と館山一子▽佐伯裕子・「アララギ」「新泉」の出発−河野愛子へ▽今井恵子・韻律について−「心の花」の栗原潔子にふれて▽川野里子・花鳥風月と第二芸術論−「潮音」と日本画▽花山多佳子・「女人短歌」群像−伝統とアプレ。
昨夏の第一回よりも、それぞれの問題意識が第二芸術論というところに集約されたため、当時の歌壇の状況や女性たちの意識がリアルに感じられた。
私が一番面白いと思ったのは、川野里子の発表である。第二芸術論が盛んに取り上げられた時期、攻撃対象になったのは短歌や俳句だけではなく、伝統的に花鳥風月や美人を描いてきた日本画も当然のこととして批判されたという点に着目した内容だった。
川野は、花鳥風月にこだわった歌誌「潮音」がいかに戦後を乗り越えようとしたかを丁寧に読み解いていった。太田水穂を主宰として創刊された「潮音」には、四賀光子、葛原妙子らが所属した。昨年『幻想の重量
−−葛原妙子の戦後短歌』を著した川野であるから、その掘り下げは緻密で、葛原が同誌に連載した「潮音花鳥譜」の文章から、彼女の美学の礎となったものを掬いあげるあたり、とても聞き応えがあった。
また、こうした象徴技法や新しい文体を求めた葛藤を、第二芸術論に対応した「パンリアル宣言」と絡めて語ったところが、非常に新鮮だった。「パンリアル」とは、「日本画壇の退嬰的アナクロニズム」に対して「狭義ではない、枠にはまらないリアリズム」、つまり「パン(=汎)リアル」を目指した概念だという。画家たちもまた歌人たちと同様、苦しみつつ新しい芸術を目指したのだった。文学以外の分野と短歌の状況を比較した川野の手法を、頼もしく感じた。
第二芸術論のみならず、日本の伝統をすべて否定しようとする戦争直後の混乱と浮薄については、「短歌」二月号で三枝昂之が、共同研究「前衛短歌とは何だったのか」の連載第一回で詳しく述べている。ローマ字を国字に採用すべきだという土岐善麿の主張など、日本語廃止論から論じ始めていることに感じ入った。
今回のシンポジウムで惜しまれる点があるとすれば、歌壇の外の状況をとらえた意見があまりなかったことだ。個々の発表内容は私の知らないことが多く、とても勉強になった。しかし、一つの歌誌、一人の歌人から戦後を見ようとする手法の発表がほとんどだった。
私は三枝が「伝統の否定」や「短歌の否定」よりも、まず「国語の否定」から論を始めた姿勢に倣いたいと思った。ローマ字表記は採用されなかったわけだが、「漢字を廃止せよ」という声は多かった。一九四六年に、内閣が当面
使うものとして取り敢えず告示した「当用漢字表(1850字)」が、一九八一年に「常用漢字表」が告示されるまで使われたことは、何を意味するのか。新聞社も政府と一緒になって、かなりいい加減な略字体を採用し、日本語を変えた。前衛短歌については、文体やモチーフ、韻律などの問題がまず語られるが、私は塚本邦雄がどんな思いで戦後の国語国字改革を受け止めたのか、なぜ一貫して正字体の漢字を用いたのか、きちんと知りたいと思う。
新聞社で長く仕事をした私にとって、紙面で漢字が制限されていること、しかも字体そのものが随分と乱暴に、法則性もなしに変えられたものであることは苦痛だった。国語政策の変遷について知れば知るほど、学校で教わった漢字を信じて疑わないこと、漢字の成り立ちや語源を知らないことを恥ずかしく思うようになった。塚本はもちろん新しい表現を求めて「前衛短歌」へ向かったのだが、そこには伝統を安易に否定しようとする言説への嫌悪、母語である日本語を本当に大切にしたい思いがあったに違いない。
今回のシンポジウムは、それぞれの発表がつながり合い、戦後という時代の雰囲気がまざまざと感じられる内容だった。そこに、もう一つ、政治や教育といった大きな底辺を見据えた論が加わったなら、さらに深みが増したと思う。シンポジウム「いま、読みなおす戦後短歌」は、三回目以降も開かれる予定だという。今度はどんなテーマで戦後短歌に迫るのか、待ち遠しくてならない。
|
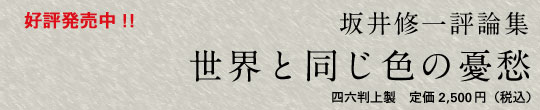
|
|