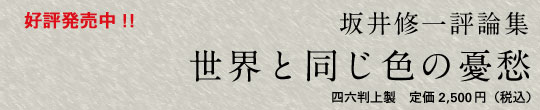自然詠のリアリティ
text 松村由利子
先日新潟を訪れた際、地元の方たちがハクチョウやヒシクイを見に福島潟へ連れて行ってくださった。太陽が昇ってしばらくすると、水鳥たちはひと群れずつ飛び立ってゆく。一列になったハクチョウが遠くの空できらきらと輝く姿は、私にとって初めて見るものだった。その後、たまたま新潟在住の歌人の作品を読む機会があった。
すみとほるきさらぎの空をわたりゆく銀の鎖のごときひとつら
佐々木澄代『銀の鎖』
非常に素直な歌だが、たぶん私は今回新潟へ行かなければ、この歌がハクチョウの群れを詠ったものだと分からなかっただろうし、歌のよさを十分に味わうことができなかったと思う。空高く飛ぶハクチョウは本当に、光線の具合によって時折、銀色の細いかけらが連なるように見えるのである。こんなふうに、風土や実景を知らなければ歌のリアリティを感じられないということも多いのかもしれない。
そんなことを考えていて思い出したのが、今年の「短歌現代」九月号に掲載された山田富士郎の評論「『ユルタンカ』を超えて」である。山田は、規範意識がなく、傾倒する歌人もいない若い歌人の作品を「ユルタンカ」と名づけ、「異性への意識や自意識はあるが、社会も自然も存在しないかのような世界」だと評している。さらに、吉本隆明が『日本語のゆくえ』(2008年1月、光文社)で、大都市に住む若い詩人には「自然に対する感受性がなくなってしまっている」と述べていることを指摘する。
「自然に対する感覚の鈍磨は短歌にとっても重大事だが、そう考える人があまりいないらしいことには危機感を感じないわけにはいかない」「若い歌人の歌に自然がほとんど出てこなくなったら、短歌の博物館入りは近いのである」と、山田が自然との交感の大切さについて繰り返していることに、私はたいへん感じ入った。
自然との交感がたっぷり味わえる歌集といえば、先日出版されたばかりの伊藤一彦の『月の夜声』(2009年11月、本阿弥書店)である。
しづかなる秋の一夜をわれは言葉、月は光の沈黙交易
かうかうと照る月光を聴き得ねば見るのみにして庭に立ち尽くす
竹林にとぐろを巻ける黒きもの百年われを待ちゐるごとし
数々の月の名歌で親しまれる伊藤であるが、この歌集にも月を詠った佳品が多い。伊藤にとって、自然はただ見るものではなく、互いに働きかけるものとリアルに捉えているところが魅力である。一首目は美しい良夜を思わせるが、月を愛でるというより月と会話をしているという風景が面
白い。「沈黙交易」という意外な結語で締めくくられているのも巧みであり、読者を独特の世界へと誘う。二首目は、「月光の訛りて降るとわれいへど誰も誰も信じてくれぬ
」という伊藤自身の歌を思い出させて愉快である。この晩に限っては月の声が聞こえなかったのだろうか。三首目の「竹林にとぐろを巻ける黒きもの」は、蛇と取ってもよいが、そう取らない方が深みが出る。百年もの歳月、何者かに待たれているという感覚は、都会ではなかなか得ることができないように思う。
しかし、こうした感覚は、自然豊かな宮崎の地に住む歌人ならではのものなのだろうか。
その年にどこかからわたしも着いた陸半球の縁ぎりぎりに
六月の信号待ちのトラックの濡れたタイヤにはりつく未来
やすたけまり「ナガミヒナゲシ」(「短歌研究」2009年9月号)
今年度の短歌研究新人賞を受賞したやすたけの作品は、不思議な魅力に満ちている。加藤治郎は選考座談会で、「自然詠という視点で読んでみるとなかなか面
白いものが出てくるのではないかと思いました」「若い人の自然に対する向かい方は、生命とセットにして歌っていくんですね」と述べている。一連のなかで、作者は時に人間であったり、帰化植物だったりして、ちょっと危うい存在感を漂わせている。
彼女が授賞式のスピーチで、「自分の歌は、性別も年齢も不詳。そして、人間なのか、人間でないものかもわからない」と話したのが、私にはたいへん印象に残っている。「ああ、柔軟な感じがとてもいいなあ」と思ったのだ。
加藤が言うように、自然と人間との関係性は、時代によって変わってゆくのではないだろうか。DNAの二重らせんの美しさや遺伝子の働きの不思議さは、人々の生命観、自然観を新たにした。もちろん広大な風景を見て畏敬の念を抱いたり、季節の移ろいに喜びを感じたりする心は、昔と変わらないだろう。人は自然に触れることで、より深く、よりリアルに詠うことができる。「ナガミヒナゲシ」の一連においても、「なつかしい野原」「国道沿い」といった言葉には、現実の自然を詠ったリアリティが感じられる。そして、きっとその先に、加藤の言う「自然詠の現代的展開」があるのだ。自然詠をよりよく鑑賞するにも、新しい自然詠を目指すにも、まずは自然を知ることが第一歩なのだと思う。
|